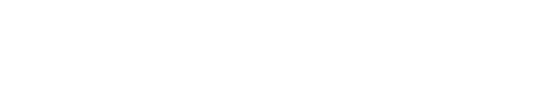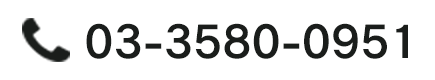SPC認証始めました!!(無料セミナー開催!)
★SPC認証無料説明会開催決定!★
お申込みはこちらから↓
プラスチックの再生利用に関するSPC認証・オンライン説明会:無料
SPC認証について
JCQAは、SPC認証を通じて、再生資源調達⇒再生原料製造⇒成形用再生材料製造へと続くSPC認証チェーンを更に強固なものとし、動脈側の信頼を勝ち取り、再生プラの更なる普及に貢献します。(SPC:Sustainable Plastics Certification)
また、審査での改善事項を活用することで、リサイクラーのレベルアップに寄与できる審査を心掛けていきます。
関連サイト:一般社団法人 サステナブル経営推進機構(SuMPO)
SPC認証関連記事:SPC認証” 国内企業8社でパイロット認証取得
SPC認証プログラムの目的と概要
経済産業省の指針であるサーキュラーエコノミーに則り、プラスチックの再生は重要な課題です。
日本では使用済プラスチックが年間約820万トン排出されますが、その内リサイクル量は約95万トンであり、マテリアルリサイクルは需要な課題です。
SPC認証プログラムは、プラスチック循環資源の再生について、適正なマテリアルリサイクルシステムを構築し、それを認証するプログラムです。
事業所もしくは工場単位(以下、認証事業所という)で認証します。
特徴
1.再生プラスチックの価値と信頼性を高め、使用者側(ブランドオーナー、成形加工メーカー等)の適正な価格評価と使用量の拡大を目指します。
2.エンドユーザー(製品機能使用者)に再生プラスチックに関する理解を促進することを目的としています。
3.プラスチック製造、販売等に関わる会員で構成する一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)が技術支援を行うので、市場ニーズとマッチした認証制度です。
認証基準および認証レベル
SPC認証は、SPC認証基準(6原則10手順)に基づき現地評価を実施します。
SPC認証基準は、品質、安全、需給バランス、環境および認証区分ごとの品質向上への取り組みを評価する項目等で構成され、これらの項目はカテゴリごとに必須項目を設定しています。
3つの認証のカテゴリを設け、再生資源調達、再生原料製造、成形用再生材料製造(コンパウンド)で認証されます。
認証取得の効果
(社内的なメリット)
・作業の標準化が進む
・多能工化への展開が期待できる
・ヒューマンエラーの防止につながることが期待できる
・工程異常への対応の体系化ができる
・変更管理への対応がより確実なものとなる
(社外的なメリット)
・SP認証制度への参画で事業所のイメージ・信頼度の向上が期待できる
・顧客のSPC認証制度への信頼感から販路拡大が期待できる
・顧客満足の向上が図れる
お問い合わせ
SPC審査部・営業部 TEL:03-3580-0951
お申込みはこちらから↓
プラスチックの再生利用に関するSPC認証・オンライン説明会:無料
SPC認証について
JCQAは、SPC認証を通じて、再生資源調達⇒再生原料製造⇒成形用再生材料製造へと続くSPC認証チェーンを更に強固なものとし、動脈側の信頼を勝ち取り、再生プラの更なる普及に貢献します。(SPC:Sustainable Plastics Certification)
また、審査での改善事項を活用することで、リサイクラーのレベルアップに寄与できる審査を心掛けていきます。
関連サイト:一般社団法人 サステナブル経営推進機構(SuMPO)
SPC認証関連記事:SPC認証” 国内企業8社でパイロット認証取得
SPC認証プログラムの目的と概要
経済産業省の指針であるサーキュラーエコノミーに則り、プラスチックの再生は重要な課題です。
日本では使用済プラスチックが年間約820万トン排出されますが、その内リサイクル量は約95万トンであり、マテリアルリサイクルは需要な課題です。
SPC認証プログラムは、プラスチック循環資源の再生について、適正なマテリアルリサイクルシステムを構築し、それを認証するプログラムです。
事業所もしくは工場単位(以下、認証事業所という)で認証します。
特徴
1.再生プラスチックの価値と信頼性を高め、使用者側(ブランドオーナー、成形加工メーカー等)の適正な価格評価と使用量の拡大を目指します。
2.エンドユーザー(製品機能使用者)に再生プラスチックに関する理解を促進することを目的としています。
3.プラスチック製造、販売等に関わる会員で構成する一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)が技術支援を行うので、市場ニーズとマッチした認証制度です。
認証基準および認証レベル
SPC認証は、SPC認証基準(6原則10手順)に基づき現地評価を実施します。
SPC認証基準は、品質、安全、需給バランス、環境および認証区分ごとの品質向上への取り組みを評価する項目等で構成され、これらの項目はカテゴリごとに必須項目を設定しています。
3つの認証のカテゴリを設け、再生資源調達、再生原料製造、成形用再生材料製造(コンパウンド)で認証されます。
認証取得の効果
(社内的なメリット)
・作業の標準化が進む
・多能工化への展開が期待できる
・ヒューマンエラーの防止につながることが期待できる
・工程異常への対応の体系化ができる
・変更管理への対応がより確実なものとなる
(社外的なメリット)
・SP認証制度への参画で事業所のイメージ・信頼度の向上が期待できる
・顧客のSPC認証制度への信頼感から販路拡大が期待できる
・顧客満足の向上が図れる
お問い合わせ
SPC審査部・営業部 TEL:03-3580-0951